令和6年度 からむし織第31期体験生募集のご案内
令和6年度の募集は締め切りました
令和6年度に事業開始を予定するからむし織体験生の募集に関するご案内です。
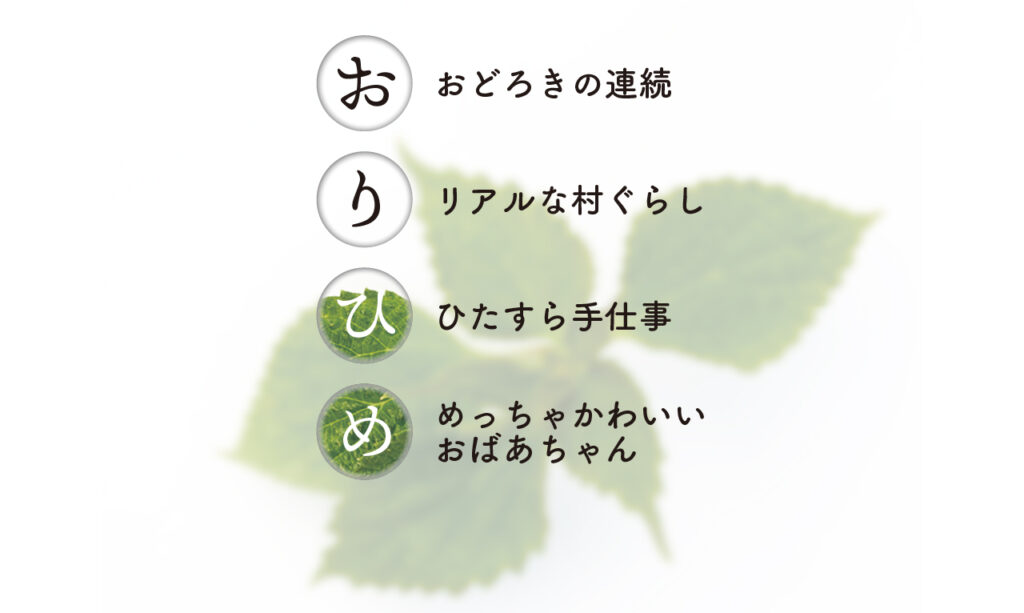
「からむし織」は、からむし(苧麻(ちょま))という植物の繊維を素材とした織物で、かつては日本各地で織られ献上布として納められた貴重なものです。
その品質は、吸湿性、速乾性に富み、肌触りも良く、夏衣としては最高級と評価されています。
ここ昭和村は、上布用高品質のからむし栽培地で、途切れることなくからむし栽培技術を伝承してきました。栽培から織りに至るほとんどの工程を手作業に頼る伝統文化は、山村にひっそりと息づき、先人達の想いを紡ぎ、心を織り続けています。






体験制度について
目的
からむしの栽培から織に至るまでの一連の作業工程と昭和村の生活文化を知っていただくとともに、村人との交流を深めていただくことを目的としています。
体験期間
2024(令和6)年5月7日から2025(令和7)年3月31日までの約11ヶ月間
体験時間及び休日
- 体験時間
午前9時から午後5時まで
※休憩は正午から午後1時まで
※体験内容により開始時間に変動があります - 休日は、土・日・祝日とし、夏期休暇・冬期休暇を設けます
※土・日・祝日に体験がある場合は休日を平日に振り替えます
体験内容
からむし織に至る一連の作業工程
- からむし畑の作業(5月)
雑草取り、からむし焼き、施肥、垣造り、根の植え替え作業 - 刈り取り、苧引き(からむしひき)(7月~8月)
成長したからむしの刈り取り、茎の表皮から繊維を取り出す作業 - 糸づくり(5月~ 12月)
からむしの繊維を細く裂き、繋ぎ、糸にする苧績み(かむしうみ)、撚り掛け、染色等 - 織り(12月~3月)
- 高機を用い、平織り帯1本を織りあげる
3月中旬には作品展を開催します。
山村生活体験(下記の体験も取り組みます)
- 直営畑による家庭菜園程度の野菜作り…ジャガイモ、大根、白菜等々
- 染色(草木染め)、わらじ作り等の生活工芸品づくり
- 郷土料理体験…笹巻き、山菜料理等
- 運動会等、村内の各種行事へ参加






体験上の条件
- 本村に住民登録をしていただきます
- 体験中の宿泊は、原則村有施設での共同生活(個室)となります
- 村の方針に従って体験していただきます
各種経費
- 体験に関する費用
- 体験に必要な「からむし」などの材料や光熱水費は村が負担します
※梅漬けの材料や陶芸等の体験経費は個人負担になります - 織機(高機)などの織りの道具は村の備品を利用します
- 体験に必要な「からむし」などの材料や光熱水費は村が負担します
- 生活費について
- 宿舎の光熱水費や灯油等の燃料費は村が負担します
※食費やガソリン代、日常の消耗品等は個人負担になります - 国民健康保険、国民年金
※加入が必要となった場合の保険料等は個人負担になります
- 宿舎の光熱水費や灯油等の燃料費は村が負担します
その他
- 体験期間中の体験に起因する身体的な傷害については、村が加入する傷害保険の範囲内で対応します
- 体験修了後も、からむしをテーマとした調査研究、技術習得などを希望する方には最長で3年間、からむし織研修生(手当有り)として引き続き村内に在住できる制度があります
募集について
募集対象
からむし織と山村生活に関心があり、心身ともに健康で、体験期間中村の各種行事に積極的に参加することができる2024(令和6)年4月1日現在の年齢が満18歳以上の方。性別、織り経験の有無は問いません。
募集人数
5名
応募方法
1.応募方法
- 写真を貼った履歴書(A4版)(市販品、またはウェブサイトに掲載の指定様式【※健康状態は必ず記載してください】)に、800字程度の応募動機(A4版・400字詰め原稿用紙、またはウェブサイトに掲載の指定様式)を添え、郵送か電子メールで提出又は直接ご持参ください
| <送付先> 〒968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島611 からむし会館内 昭和村産業建設課 からむし振興係 宛 電話:0241-57-2116/FAX:0241-57-3044 mail:karamushi(at)showavill.jp ※(at)を@に変更してご送付ください。 |
2.応募期間
2023(令和5)年10月31日(火)まで
※郵送及び電子メール、直接持参による受付は上記必着とします
※直接持参される方は、応募期間内の土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間内に受付ます
審査方法
1.一次選考
提出された履歴書と応募動機により書類選考を行います。結果は11月中旬までにお知らせします
2.二次選考
書類選考の合格者に対し実施します。事業説明を兼ねて2日間で行います
日時…令和5年11月25日(土) PM、オリエンテーション及び村内の案内
令和5年11月26日(日) AM、面接
※ 宿泊は各自手配してください 村内宿泊施設の情報はこちら
3.採否
2023(令和5)年12月15日(金)までに、郵送により本人宛て書面でお知らせします
その他
1.合格者の入村について
2024(令和6)年5月1日(水)から6日(月)の間に入村(引っ越し)していただきます
2.お問い合せ先
| 昭和村産業建設課からむし振興係 電話:0241-57-2116(直通)/ FAX:0241-57-3044 E-mail:karamushi(at)showavill.jp ※(at)を@に変更してご送付ください。 |
修了後について
体験生修了後も、また一年からむしに挑戦したい、もっとからむしのことを知りたい、 村で暮らすじいちゃんばあちゃんの知恵を学びたいなど、引き続き村の生活を希望される方が多くいらっしゃいます。
村では、からむしをテーマとした調査研究、技術習得などを希望する方に、 「からむし織研修生制度」(手当の支給あり、最長3年間)を設け、引き続き村の暮らしを続けていただいています。 現在、約30名のからむし織体験修了生が昭和村に定住され、各方面で活躍されています。
修了生の声
-渡し舟-編『なかよく やれますか?』
織姫の採用面接で織姫の先生だったおばあちゃんの、面接での質問です。 その時は、なんだか当たり前の質問をするな~と思って、 簡単に「できます。」と答えてしまったけれども。 暮らしてみて、この言葉が、 ここで暮らして行くうえでとても重みのある大切な質問だったとわかります。 雪が降って立ち往生していたら、通りがかりの人が絶対声をかけてくれるし、 野菜が上手にできなかったら、自分たちの分を分けてくれる。 互いに互いを思いやる、人が生きて行く上で一番大切なことを、 お婆ちゃんは私たちに教えてくれていたのです。 この村に「からむし」が残ってきたことは、 この村の偶然ではなく必然だったということが、暮らしぶりから分かります。 空気も、ごはんも、季節のうつろいも、来てみないと分からなかったこと。 どんな、立派な学校よりも沢山の事を学ばせてくれています。

からむし織体験生制度についてより詳しく知る
灯台もと暮らし協働企画
Webメディア「灯台もと暮らし」との協働企画で、 からむし織体験生事業の特集記事を掲載しています。
1. はじめに「土からうまれた糸を継ぐ」
2. 畑から布がつくられる不思議。
3. からむし布のこれからを探りながら。渡し舟
4. 『もの』を生み出す暮らしかた
5. ここで根付けなかったら『帰れよぉ』って言うの。
6. 村を出ると決め、直前に取りやめた。
7. 織姫さんに託された『想い』

